article

【TCR × RETO】ランニングブランドが、なぜコーヒー?
text:Yuki Yoshida コラボコーヒーの発売にあたって複数人にお話を伺うなかで、何度となく出てきたフレーズです。それも皆、ナチュラルに言うんです。 なぜだろう? ランナーとコーヒーには、理論と感覚に裏付けされた深い関係性があるようです。 今回は、プロランナーの神野大地と、RETO事業の責任者でありランナー(サブ2.5)でもある高木聖也にインタビュー。「コーヒーの取り入れ方」や「ランナーとコーヒーの関係性」、「コラボコーヒーへの想い」を語ってもらいました。 例に漏れずコーヒーが好きな二人のお話をもとに、「ランニングブランドが、なぜコーヒー?」を紐解いていきたいと思います。 「RETOから、いつかコーヒーを出せればと思っていた」 高木聖也(以下、高木):自分がコーヒーを好きというのもあり、コーヒーとRETOを絡められたらとずっと思っていて。今回、それが実現した形です。 走る前にコーヒーを飲むエリート選手もいるくらい、コーヒーはランナーにとって身近な存在だと感じています。統計をとったわけではないですが、ランナーにコーヒーを好きな人が多い印象があって。「走る前に、コーヒー1杯」「ジョグした後に、カフェに寄る」などを、自然に実践している人が多いんです。神野もよく飲んでます。 神野大地(以下、神野):僕もコーヒーが好きで、1日に2杯くらい飲んでいます。朝ご飯を食べた後に1杯、お昼ご飯の後に1杯が基本です。自宅に豆を挽く機械があるので、家にいる時はそれを使って。カフェもよく利用します。 コーヒーを日常に取り入れるようになったきっかけは? ── コーヒーを習慣にされたのはいつからですか?今のスタイルが確立された経緯を教えてください。 神野:実は僕、元々コーヒー飲めなかったんです。大学生の頃は、どうしてもおいしいと思えなくて。聖也さんを含め、陸上部内でコーヒーを飲んでる人は多かったです。朝から自分で淹れている人、部屋に缶コーヒーを常備している人、スタイルは色々でした。 コーヒーを好きになったのは、社会人1年目の頃、日本陸連の選抜合宿に参加した時の偶然の出来事がきっかけです。朝食後、「コーヒー飲む人〜?」って聞かれた時に、選手だけじゃなく、スタッフさんを含めたその場の全員が手を挙げていて。僕はブラックは飲めなかったんですけど、砂糖とミルクを入れれば飲めたので、それを飲もうと思って手を挙げました。 次に「お砂糖とミルクいる人〜?」って聞かれた時、誰も手を挙げなくて。躊躇してたら、挙げ損ねてしまいました(笑)。その日は頑張ってブラックコーヒーを飲みました。 2日目、今日こそは砂糖とミルクをもらおうと思っていたら、聞かれなくなったんです(笑)。それはそうですよね、1日目で全員ブラックがいいってわかってたので。それからは、毎朝、当たり前のようにブラックコーヒーを提供していただく日々が続きました。 そうすると、7日目頃、本当に不思議なんですけど、「そろそろコーヒーかな?」と待ち望んでる自分がいました。それから、朝のコーヒーが日課になりました。 あんなに苦手だったコーヒーの味が、今では本当に大好きで。今はブラック一択です。 カフェインによるパフォーマンスアップ、実際どう? ── ランナーがよくコーヒーを飲んでいるのは、何かの効果を期待しているからでしょうか?「目が覚める」「集中力が上がる」などはよく聞きますが、それと関係がありますか? 高木:特に持久系のスポーツにおいては、カフェインの効果に関する確かなエビデンスが存在します。コーヒー好きのランナー全員が効果を期待して飲んでいるわけではないと思いますが、大会前に適正な量のカフェインを摂取すべきという見解があるのは事実です。 ── 何か実体験はありますか? 高木:トレイルランニングで100kmを超えるレースに出場する時に、戦略的にカフェインを摂っています。カフェインのお陰と言いきってしまうのは難しいんですが、身体が相当疲弊している時にカフェインを摂ると、楽になるんです。そういう時に効果を実感します。 「信越五岳トレイルランニングレース」110kmでは目標達成を果たした 神野:カフェインを摂ることで、集中力が高まるのを感じたことは何度もあります。ただ、僕の場合は、毎日飲んでいると効果を得にくいと思っていて。 過去に実践したことがあるんですけど、大事なレースの前って、カフェインを抜くんです。1週間程カフェインを抜いて、当日のレースの1時間前に飲む。そうすると、目がバキバキになります。それくらいカフェインって偉大で。僕の周りにも、そういう風にカフェインを摂っているマラソン選手はいます。...
【TCR × RETO】ランニングブランドが、なぜコーヒー?
text:Yuki Yoshida コラボコーヒーの発売にあたって複数人にお話を伺うなかで、何度となく出てきたフレーズです。それも皆、ナチュラルに言うんです。 なぜだろう? ランナーとコーヒーには、理論と感覚に裏付けされた深い関係性があるようです。 今回は、プロランナーの神野大地と、RETO事業の責任者でありランナー(サブ2.5)でもある高木聖也にインタビュー。「コーヒーの取り入れ方」や「ランナーとコーヒーの関係性」、「コラボコーヒーへの想い」を語ってもらいました。 例に漏れずコーヒーが好きな二人のお話をもとに、「ランニングブランドが、なぜコーヒー?」を紐解いていきたいと思います。 「RETOから、いつかコーヒーを出せればと思っていた」 高木聖也(以下、高木):自分がコーヒーを好きというのもあり、コーヒーとRETOを絡められたらとずっと思っていて。今回、それが実現した形です。 走る前にコーヒーを飲むエリート選手もいるくらい、コーヒーはランナーにとって身近な存在だと感じています。統計をとったわけではないですが、ランナーにコーヒーを好きな人が多い印象があって。「走る前に、コーヒー1杯」「ジョグした後に、カフェに寄る」などを、自然に実践している人が多いんです。神野もよく飲んでます。 神野大地(以下、神野):僕もコーヒーが好きで、1日に2杯くらい飲んでいます。朝ご飯を食べた後に1杯、お昼ご飯の後に1杯が基本です。自宅に豆を挽く機械があるので、家にいる時はそれを使って。カフェもよく利用します。 コーヒーを日常に取り入れるようになったきっかけは? ── コーヒーを習慣にされたのはいつからですか?今のスタイルが確立された経緯を教えてください。 神野:実は僕、元々コーヒー飲めなかったんです。大学生の頃は、どうしてもおいしいと思えなくて。聖也さんを含め、陸上部内でコーヒーを飲んでる人は多かったです。朝から自分で淹れている人、部屋に缶コーヒーを常備している人、スタイルは色々でした。 コーヒーを好きになったのは、社会人1年目の頃、日本陸連の選抜合宿に参加した時の偶然の出来事がきっかけです。朝食後、「コーヒー飲む人〜?」って聞かれた時に、選手だけじゃなく、スタッフさんを含めたその場の全員が手を挙げていて。僕はブラックは飲めなかったんですけど、砂糖とミルクを入れれば飲めたので、それを飲もうと思って手を挙げました。 次に「お砂糖とミルクいる人〜?」って聞かれた時、誰も手を挙げなくて。躊躇してたら、挙げ損ねてしまいました(笑)。その日は頑張ってブラックコーヒーを飲みました。 2日目、今日こそは砂糖とミルクをもらおうと思っていたら、聞かれなくなったんです(笑)。それはそうですよね、1日目で全員ブラックがいいってわかってたので。それからは、毎朝、当たり前のようにブラックコーヒーを提供していただく日々が続きました。 そうすると、7日目頃、本当に不思議なんですけど、「そろそろコーヒーかな?」と待ち望んでる自分がいました。それから、朝のコーヒーが日課になりました。 あんなに苦手だったコーヒーの味が、今では本当に大好きで。今はブラック一択です。 カフェインによるパフォーマンスアップ、実際どう? ── ランナーがよくコーヒーを飲んでいるのは、何かの効果を期待しているからでしょうか?「目が覚める」「集中力が上がる」などはよく聞きますが、それと関係がありますか? 高木:特に持久系のスポーツにおいては、カフェインの効果に関する確かなエビデンスが存在します。コーヒー好きのランナー全員が効果を期待して飲んでいるわけではないと思いますが、大会前に適正な量のカフェインを摂取すべきという見解があるのは事実です。 ── 何か実体験はありますか? 高木:トレイルランニングで100kmを超えるレースに出場する時に、戦略的にカフェインを摂っています。カフェインのお陰と言いきってしまうのは難しいんですが、身体が相当疲弊している時にカフェインを摂ると、楽になるんです。そういう時に効果を実感します。 「信越五岳トレイルランニングレース」110kmでは目標達成を果たした 神野:カフェインを摂ることで、集中力が高まるのを感じたことは何度もあります。ただ、僕の場合は、毎日飲んでいると効果を得にくいと思っていて。 過去に実践したことがあるんですけど、大事なレースの前って、カフェインを抜くんです。1週間程カフェインを抜いて、当日のレースの1時間前に飲む。そうすると、目がバキバキになります。それくらいカフェインって偉大で。僕の周りにも、そういう風にカフェインを摂っているマラソン選手はいます。...

毎日飲むコーヒーのこと、どれだけ知っていますか? おいしいコーヒーが未来にもたらす変化とは
text:Yuki Yoshida 「1日に500円以上使ってる人もいると思うんですよ、コーヒーに。そうすると、年間20万円近く。それだけお金を使うんだったら、もっとコーヒーに興味を持ってもよくないですか?」と話すのは、スペシャルティコーヒー専門店「TERRA COFFEE ROASTERS」(株式会社ハーモニー/TCR)の西村紀彦代表。 そして、こうとも。 「レストランに行ったとして、『これは〇〇産のトマトを使ったカプレーゼです』『メインには〇〇産のお肉を使っていて、ソースは〇〇風に仕上げています』『デザートは〇〇牧場の生乳を使ったアイスです』『最後に、食後のコーヒーです』。食後のコーヒーになった瞬間、めちゃくちゃトーンダウンするんですよ」。 ……確かに。普段、いかにコーヒーに対して“何となく”だったのかを思い知らされました。 今回、RETOとTCRのコラボコーヒーが発売されるにあたって、西村代表にインタビュー。コーヒーへの想いやこれまでの歩みについてお話を伺っていると、コーヒーの未来の話にたどり着いていきました。 コーヒーとの出会いは、スポーツがきっかけだった 2021年10月にオープンしたTERRA COFFEE ROASTERS。拠点は大阪。今や、全国に取引先やファンがいる人気店です。 ── 元々違う業界にいらっしゃったとか。コーヒー業界に入られたきっかけを教えてください。 2011年に、事務用品メーカーへの就職を機に、大阪から東京へ出て来ました。少し時間ができた時、ふらっとロードバイク専門店に入ったら、カッコいい自転車がたくさん並んでいて。以前から「ツール・ド・フランス」を観ていたこともあり、その場で買って、自転車に乗り始めました。 どんどん遠くに行けるようになって、1週間に300〜400kmも乗っていて。自転車で遠くに行った時、何を求めるか?っていうと、おいしいコーヒーとパンでした。そのうち、カフェライドをしだして、全国色んな所にコーヒーを飲みに行きました。 スポーツをする人って、コーヒー好きな人が多いんです。自転車乗りの人たちと交流するなかで、コーヒーに触れる機会が増えていきました。そうすると、徐々に「コーヒーって味ちゃうな」って思いだしまして。そこからは段々マニアックになってきて。SNSや業界誌を見て、海外からコーヒーを仕入れ始めました。 自分で生豆を仕入れて、プロが使うような焙煎機を買って。問屋と個人で付き合うようになりました。一人じゃ飲みきれないので、コーヒー豆をコーヒーやってる人にあげだして。そうすると「このコーヒー何ですか?」って。「あれ、このブランド知らんのか?」と。 日本のコーヒーリテラシーを上げる必要性を感じ、起業 ── 小さな違和感が起業のきっかけでしょうか?その後、TERRA COFFEE ROASTERSをオープンされるまでの経緯を教えてください。 そのうち、海外のバリスタの大会を観るようになっていて。「このドリッパーほしいな」とか「このグラインダー使ってみたいな」とか思うんです。商社に行って「売ってますか?」って聞くと、「それ何ですか?」って。それで改めて思ったのが、日本ってすごくコーヒーのリテラシーが低いということでした。 コーヒーは世界で1番飲まれている飲料です。日本の消費量は世界で4番目。この島国で、これだけコーヒーを飲んでいるにも関わらず、蓋を開けてみると、いつ焙煎したかわからないような、どの国のものか明確になっていないような、生産者の顔が見えないようなコーヒーばっかり飲んでいて。で、「日本のコーヒーのリテラシーを上げていかなあかん」と思いました。 結局、みんな分かってないんです。食材にこだわっているレストランでも、「これ、どこのコーヒーですか?」って聞くと、「〇〇です」って、大手の社名を挙げるんです。これって、「TCR(西村代表の会社)のコーヒーです」って言ってるのと同じことで。「いや、知らんし」みたいな(笑)。だから、本当にシェフも知らないし、コーヒーをどこに頼んだらいいかなんて、誰もわからないんですよ。 ── なるほど。それで起業を? サラリーマンをしながら、コーヒーのリサーチを進めるなかで、めちゃくちゃブルーオーシャンだと思ったんです。けど、周囲は、僕がコーヒー屋で独立すると言ったとき、全員反対しました。「食べていけんの?」って。...
毎日飲むコーヒーのこと、どれだけ知っていますか? おいしいコーヒーが未来にもたらす変化とは
text:Yuki Yoshida 「1日に500円以上使ってる人もいると思うんですよ、コーヒーに。そうすると、年間20万円近く。それだけお金を使うんだったら、もっとコーヒーに興味を持ってもよくないですか?」と話すのは、スペシャルティコーヒー専門店「TERRA COFFEE ROASTERS」(株式会社ハーモニー/TCR)の西村紀彦代表。 そして、こうとも。 「レストランに行ったとして、『これは〇〇産のトマトを使ったカプレーゼです』『メインには〇〇産のお肉を使っていて、ソースは〇〇風に仕上げています』『デザートは〇〇牧場の生乳を使ったアイスです』『最後に、食後のコーヒーです』。食後のコーヒーになった瞬間、めちゃくちゃトーンダウンするんですよ」。 ……確かに。普段、いかにコーヒーに対して“何となく”だったのかを思い知らされました。 今回、RETOとTCRのコラボコーヒーが発売されるにあたって、西村代表にインタビュー。コーヒーへの想いやこれまでの歩みについてお話を伺っていると、コーヒーの未来の話にたどり着いていきました。 コーヒーとの出会いは、スポーツがきっかけだった 2021年10月にオープンしたTERRA COFFEE ROASTERS。拠点は大阪。今や、全国に取引先やファンがいる人気店です。 ── 元々違う業界にいらっしゃったとか。コーヒー業界に入られたきっかけを教えてください。 2011年に、事務用品メーカーへの就職を機に、大阪から東京へ出て来ました。少し時間ができた時、ふらっとロードバイク専門店に入ったら、カッコいい自転車がたくさん並んでいて。以前から「ツール・ド・フランス」を観ていたこともあり、その場で買って、自転車に乗り始めました。 どんどん遠くに行けるようになって、1週間に300〜400kmも乗っていて。自転車で遠くに行った時、何を求めるか?っていうと、おいしいコーヒーとパンでした。そのうち、カフェライドをしだして、全国色んな所にコーヒーを飲みに行きました。 スポーツをする人って、コーヒー好きな人が多いんです。自転車乗りの人たちと交流するなかで、コーヒーに触れる機会が増えていきました。そうすると、徐々に「コーヒーって味ちゃうな」って思いだしまして。そこからは段々マニアックになってきて。SNSや業界誌を見て、海外からコーヒーを仕入れ始めました。 自分で生豆を仕入れて、プロが使うような焙煎機を買って。問屋と個人で付き合うようになりました。一人じゃ飲みきれないので、コーヒー豆をコーヒーやってる人にあげだして。そうすると「このコーヒー何ですか?」って。「あれ、このブランド知らんのか?」と。 日本のコーヒーリテラシーを上げる必要性を感じ、起業 ── 小さな違和感が起業のきっかけでしょうか?その後、TERRA COFFEE ROASTERSをオープンされるまでの経緯を教えてください。 そのうち、海外のバリスタの大会を観るようになっていて。「このドリッパーほしいな」とか「このグラインダー使ってみたいな」とか思うんです。商社に行って「売ってますか?」って聞くと、「それ何ですか?」って。それで改めて思ったのが、日本ってすごくコーヒーのリテラシーが低いということでした。 コーヒーは世界で1番飲まれている飲料です。日本の消費量は世界で4番目。この島国で、これだけコーヒーを飲んでいるにも関わらず、蓋を開けてみると、いつ焙煎したかわからないような、どの国のものか明確になっていないような、生産者の顔が見えないようなコーヒーばっかり飲んでいて。で、「日本のコーヒーのリテラシーを上げていかなあかん」と思いました。 結局、みんな分かってないんです。食材にこだわっているレストランでも、「これ、どこのコーヒーですか?」って聞くと、「〇〇です」って、大手の社名を挙げるんです。これって、「TCR(西村代表の会社)のコーヒーです」って言ってるのと同じことで。「いや、知らんし」みたいな(笑)。だから、本当にシェフも知らないし、コーヒーをどこに頼んだらいいかなんて、誰もわからないんですよ。 ── なるほど。それで起業を? サラリーマンをしながら、コーヒーのリサーチを進めるなかで、めちゃくちゃブルーオーシャンだと思ったんです。けど、周囲は、僕がコーヒー屋で独立すると言ったとき、全員反対しました。「食べていけんの?」って。...
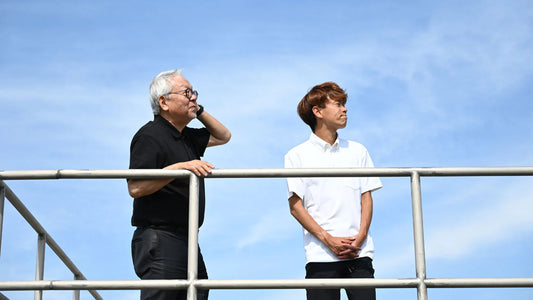
「異端児」という共通項に見る、IKEUCHI ORGANICと神野大地のものづくり
Text: yuki yoshida 愛媛県・今治のタオルメーカー「IKEUCHI ORGANIC」とプロランナーの神野大地、両者にはきっと、共通項があるはずです。 ……というのも、IKEUCHI ORGANICと“IKEUCHI ORGANICが好きな人たち”との間には、確固たる何かがあって、両者が同じ方向を向いている、と感じられるから。 IKEUCHI ORGANICが、どうして神野大地とものづくりをしようと思ったのか? IKEUCHI ORGANICの池内計司代表と広報の牟田口武志さんにお話を伺いました。 池内計司代表 牟田口武志さん画像提供:IKEUCHI ORGANIC 株式会社 「世界一、安全で精密なタオル」を掲げるIKEUCHI ORGANIC ── まずはじめに、簡単に自己紹介をお願いします。 池内計司代表(以下、池内):代表の池内です。現在のパナソニックに入って、オーディオブランドのテクニクスの立ち上げから12年ほどそちらにいました。その後、今治の家業であるタオルのほうに帰ってきて現在に至ります。 帰る直前に創業者の先代が亡くなったので、私自身は引き継ぎがないまま社長をやっているという形だったんですが、今は三代目の阿部に社長をしてもらっていまして、私はひたすらつくりたいものを勝手につくって、という気楽な立場でやっています。 ── ありがとうございます。牟田口さん、お願いします。 牟田口武志さん(以下、牟田口):私は今から7年前にIKEUCHI ORGANICに入社しました。その前は、大学を出て映画会社やTSUTAYAの会社、直近だとAmazonにいました。IT畑が長かったので、実態のあるものやものづくりにすごく憧れていて、きちんと手触り感のあるものを直接お客様に届けていきたいというのがあり、ちょうどタイミングと縁が重なって7年前に入社をしています。 現在は、広報のほかに営業の責任者でもありまして、WEBまわりや店舗、営業などをみています。マーケティングに関しても自分が担当しています。資格は、タオルソムリエという資格を持っています。これはうちの社員が全員取らないといけない資格で……。 池内:僕は持っていないです。...
「異端児」という共通項に見る、IKEUCHI ORGANICと神野大地のものづくり
Text: yuki yoshida 愛媛県・今治のタオルメーカー「IKEUCHI ORGANIC」とプロランナーの神野大地、両者にはきっと、共通項があるはずです。 ……というのも、IKEUCHI ORGANICと“IKEUCHI ORGANICが好きな人たち”との間には、確固たる何かがあって、両者が同じ方向を向いている、と感じられるから。 IKEUCHI ORGANICが、どうして神野大地とものづくりをしようと思ったのか? IKEUCHI ORGANICの池内計司代表と広報の牟田口武志さんにお話を伺いました。 池内計司代表 牟田口武志さん画像提供:IKEUCHI ORGANIC 株式会社 「世界一、安全で精密なタオル」を掲げるIKEUCHI ORGANIC ── まずはじめに、簡単に自己紹介をお願いします。 池内計司代表(以下、池内):代表の池内です。現在のパナソニックに入って、オーディオブランドのテクニクスの立ち上げから12年ほどそちらにいました。その後、今治の家業であるタオルのほうに帰ってきて現在に至ります。 帰る直前に創業者の先代が亡くなったので、私自身は引き継ぎがないまま社長をやっているという形だったんですが、今は三代目の阿部に社長をしてもらっていまして、私はひたすらつくりたいものを勝手につくって、という気楽な立場でやっています。 ── ありがとうございます。牟田口さん、お願いします。 牟田口武志さん(以下、牟田口):私は今から7年前にIKEUCHI ORGANICに入社しました。その前は、大学を出て映画会社やTSUTAYAの会社、直近だとAmazonにいました。IT畑が長かったので、実態のあるものやものづくりにすごく憧れていて、きちんと手触り感のあるものを直接お客様に届けていきたいというのがあり、ちょうどタイミングと縁が重なって7年前に入社をしています。 現在は、広報のほかに営業の責任者でもありまして、WEBまわりや店舗、営業などをみています。マーケティングに関しても自分が担当しています。資格は、タオルソムリエという資格を持っています。これはうちの社員が全員取らないといけない資格で……。 池内:僕は持っていないです。...

【IKEUCHI ORGANIC × RETO】特別に、コラボタオルの設計図を見せてもらいました
Text: yuki yoshida 建物を建てるときに設計図が必要なように、タオルにも設計図がある……ということを、知りませんでした。IKEUCHI ORGANIC × RETOのコラボタオルも例外なく、設計図がなければ完成していません。 設計図には、つくり手の想いが込められている こちらが、今回のコラボタオル「IKEUCHI ORGANIC × RETO スポーツタオル」の設計図。 「どんなタオルをつくるか」がまとめられた設計図には、神野大地がどんなタオルを望んだか?が詰まっています。ただ、ご覧のとおり、素人が見ただけでは何が何だか分かりません。 今回は、コラボタオルの設計案を担当されているIKEUCHI ORGANICの池内計司代表と神野大地に、コラボタオルの設計図ができるまでにどんなやりとりがあったのかを聞きました。 全部で54万6000通り。設計に“らしさ”が表れる ── 設計というお仕事について教えてください。 池内計司代表(以下、池内):タオルは設計をして、最終的には織機というもので織っていきます。織機は基本的にはコンピューターで動いているので、コンピューターのデータを送り込まないといけません。そのデータが設計図です。 コンピューターのデータに関しては、僕みたいなアバウトな人間だとうまくいかないので(笑)、矢野という設計担当者がきっちり落とし込んで工場に正確に伝えるという感じでやっています。 ── 企画や設計案は池内代表が、細かいところは矢野さんが、というイメージでしょうか? 池内:そうです。僕はわりと、生産性の良し悪しなどを度外視して、最終的にお客さんが喜んでくれそうなものを設計します。けど、工場サイドはそういうわけにはいかなくて。矢野は大体工場の責任者と私の間に挟まって非常にツラい思いをしているという……(笑)。 ── 設計の要素は糸の太さやパイルの長さになるのでしょうか。どうやってタオルごとの違いを出していくのか教えていただけますか? 池内:タオルには、お客さんが実際に触るパイルといわれるものと、表からは見えないけれど下に隠れている縦糸横糸があります。縦糸方向の密度、横糸方向の密度、それとパイルの長さなど、タオルとして実際にありそうなところを掛け算していくと大体54万6000通りくらいあるんです。 それで、IKEUCHI ORGANICは、タオルの風合いの基本パターンでいうと10〜15種類にしぼっています。54万6000通りのどこをチョイスするかというのは、その会社の設計者の考えみたいなところでチョイスしているわけで、それによってタオルは大きく変わります。 だから、その10〜15くらいの種類が、IKEUCHI...
【IKEUCHI ORGANIC × RETO】特別に、コラボタオルの設計図を見せてもらいました
Text: yuki yoshida 建物を建てるときに設計図が必要なように、タオルにも設計図がある……ということを、知りませんでした。IKEUCHI ORGANIC × RETOのコラボタオルも例外なく、設計図がなければ完成していません。 設計図には、つくり手の想いが込められている こちらが、今回のコラボタオル「IKEUCHI ORGANIC × RETO スポーツタオル」の設計図。 「どんなタオルをつくるか」がまとめられた設計図には、神野大地がどんなタオルを望んだか?が詰まっています。ただ、ご覧のとおり、素人が見ただけでは何が何だか分かりません。 今回は、コラボタオルの設計案を担当されているIKEUCHI ORGANICの池内計司代表と神野大地に、コラボタオルの設計図ができるまでにどんなやりとりがあったのかを聞きました。 全部で54万6000通り。設計に“らしさ”が表れる ── 設計というお仕事について教えてください。 池内計司代表(以下、池内):タオルは設計をして、最終的には織機というもので織っていきます。織機は基本的にはコンピューターで動いているので、コンピューターのデータを送り込まないといけません。そのデータが設計図です。 コンピューターのデータに関しては、僕みたいなアバウトな人間だとうまくいかないので(笑)、矢野という設計担当者がきっちり落とし込んで工場に正確に伝えるという感じでやっています。 ── 企画や設計案は池内代表が、細かいところは矢野さんが、というイメージでしょうか? 池内:そうです。僕はわりと、生産性の良し悪しなどを度外視して、最終的にお客さんが喜んでくれそうなものを設計します。けど、工場サイドはそういうわけにはいかなくて。矢野は大体工場の責任者と私の間に挟まって非常にツラい思いをしているという……(笑)。 ── 設計の要素は糸の太さやパイルの長さになるのでしょうか。どうやってタオルごとの違いを出していくのか教えていただけますか? 池内:タオルには、お客さんが実際に触るパイルといわれるものと、表からは見えないけれど下に隠れている縦糸横糸があります。縦糸方向の密度、横糸方向の密度、それとパイルの長さなど、タオルとして実際にありそうなところを掛け算していくと大体54万6000通りくらいあるんです。 それで、IKEUCHI ORGANICは、タオルの風合いの基本パターンでいうと10〜15種類にしぼっています。54万6000通りのどこをチョイスするかというのは、その会社の設計者の考えみたいなところでチョイスしているわけで、それによってタオルは大きく変わります。 だから、その10〜15くらいの種類が、IKEUCHI...

すべては「IKEUCHI ORGANICが好きだから」。スポーツタオルでのコラボが叶った理由
Text: yuki yoshida 「たぶん『好きです』みたいなことしか伝えてないかもしれないです(笑)」と柔らかい笑顔で話すのは、RETO事業の責任者であり、神野大地のマネジメントを務める高木聖也。 RETOとIKEUCHI ORGANICのコラボタオル「IKEUCHI ORGANIC × RETO スポーツタオル」を企画・開発するにあたって、今回は、高木から神野に“IKEUCHI ORGANICがどんなにいいか”をプレゼン。神野も、自宅でIKEUCHI ORGANICのアイテムを愛用するくらい今ではすっかりファンになっていますが、コラボをするにあたって、二人の間でどんなコミュニケーションがあったのでしょうか。 プロランナーの神野大地とRETO事業の責任者である高木聖也が、たっぷりと、IKEUCHI ORGANICへの愛を語っています。 なんで、IKEUCHI ORGANICだったのか? ── 今回なぜ、IKEUCHI ORGANICとコラボしたいと思ったのでしょうか。 高木聖也(以下、高木):僕がIKEUCHI ORGANICのファンで。本当に、ものがすごくよくて、基本的にはそこがすべてです。あとは、メディアの発信でより好きになっていったというのがリアルなところで、WEBメディア「イケウチな人たち。」やnoteなどの読み物からこだわりが見えてくるのがいいなと思っていました。 実際に広報の牟田口さんとやりとりさせていただいても、「自分の周りのアスリートに提供できますよ」といった話をしたら、そこにも結構条件があって。「ぜひ使ってください」という感じでただ商品を提供するのではなくて、「このタオルを本当にいいと思ってくれる方じゃないと……」と言われて、そういうところが逆にすごくいいなと感じたのもあります。 ── 高木さんがIKEUCHI ORGANICのファンになったのは、美容師の方のnoteがきっかけだったとか。普段から、人の勧めに耳を傾けるタイプなんでしょうか?その発信を見て、どうして使ってみようと思ったのですか? 高木:結構前のことなので鮮明には覚えていないのですが、IKEUCHI ORGANICのことは、牟田口さんの発信や共通の知人のSNSを通してなんとなく知っていました。それで、自分のタイムラインに流れてきた記事を読んで、買ってみたいと思いました。それはたぶん、noteの文章が響いたというのもあったと思いますが、そんなに深く考えずに買ったという感じです。そういうことがよくあるかというと、普段はそんなにないです。 ── IKEUCHI ORGANICを潜在的に知っていて、タイミングが合って購入に至ったということですね。...
すべては「IKEUCHI ORGANICが好きだから」。スポーツタオルでのコラボが叶った理由
Text: yuki yoshida 「たぶん『好きです』みたいなことしか伝えてないかもしれないです(笑)」と柔らかい笑顔で話すのは、RETO事業の責任者であり、神野大地のマネジメントを務める高木聖也。 RETOとIKEUCHI ORGANICのコラボタオル「IKEUCHI ORGANIC × RETO スポーツタオル」を企画・開発するにあたって、今回は、高木から神野に“IKEUCHI ORGANICがどんなにいいか”をプレゼン。神野も、自宅でIKEUCHI ORGANICのアイテムを愛用するくらい今ではすっかりファンになっていますが、コラボをするにあたって、二人の間でどんなコミュニケーションがあったのでしょうか。 プロランナーの神野大地とRETO事業の責任者である高木聖也が、たっぷりと、IKEUCHI ORGANICへの愛を語っています。 なんで、IKEUCHI ORGANICだったのか? ── 今回なぜ、IKEUCHI ORGANICとコラボしたいと思ったのでしょうか。 高木聖也(以下、高木):僕がIKEUCHI ORGANICのファンで。本当に、ものがすごくよくて、基本的にはそこがすべてです。あとは、メディアの発信でより好きになっていったというのがリアルなところで、WEBメディア「イケウチな人たち。」やnoteなどの読み物からこだわりが見えてくるのがいいなと思っていました。 実際に広報の牟田口さんとやりとりさせていただいても、「自分の周りのアスリートに提供できますよ」といった話をしたら、そこにも結構条件があって。「ぜひ使ってください」という感じでただ商品を提供するのではなくて、「このタオルを本当にいいと思ってくれる方じゃないと……」と言われて、そういうところが逆にすごくいいなと感じたのもあります。 ── 高木さんがIKEUCHI ORGANICのファンになったのは、美容師の方のnoteがきっかけだったとか。普段から、人の勧めに耳を傾けるタイプなんでしょうか?その発信を見て、どうして使ってみようと思ったのですか? 高木:結構前のことなので鮮明には覚えていないのですが、IKEUCHI ORGANICのことは、牟田口さんの発信や共通の知人のSNSを通してなんとなく知っていました。それで、自分のタイムラインに流れてきた記事を読んで、買ってみたいと思いました。それはたぶん、noteの文章が響いたというのもあったと思いますが、そんなに深く考えずに買ったという感じです。そういうことがよくあるかというと、普段はそんなにないです。 ── IKEUCHI ORGANICを潜在的に知っていて、タイミングが合って購入に至ったということですね。...

職人の感性が「一番の履き心地」を生み出している ──神野大地×靴下老舗メーカー社長対談(後編)
Text: yuki yoshida 2022年4月、神野大地が手がけるブランド「RETO(レト)」からランニングソックスが販売スタート。同商品は、日本三大靴下産地である兵庫県加古川市に自社工場を構えるUNIVAL(株式会社ユニバル)と共同開発し、約1年かけて完成した。 2月には実際に兵庫県加古川市にある工場を見学。本記事では、工場見学後にUNIVALの横山社長と神野が行った対談を公開する。 後編では、普段あまり知る機会がない靴下製造の“中の話”に触れていく。横山社長のこだわりやものづくりにかける想いを垣間見ることができるだろう。 ランニングには、ランニングに一番適した靴下を 神野:お話を聞いていると、靴下ってとても繊細ですよね。作るのにも時間がかかっていたり、そんなに高い商品ではなかったりがあると思うんですけど、どうして靴下にこだわり続けているのかっていうのは何か理由がありますか? 横山:そうですねー。うちの会社は製造も踏まえますと56年目に入っていて、創始者がうちの父で、私が二代目っていう形でやらせていただいてます。 兵庫県の加古川市の地場産業として靴下の製造があります。これは私もうちの父から聞いたんですけど、加古川市の志方町っていうところは昔綿花を栽培してたところで、そういう繋がりで靴下っていうのがこの地に生まれました。もっと古くからいうと、ある方が中国から編み機を1台持って帰ってきて、ここで育った綿花を紡いで靴下を作ったっていうのが最初だと聞いたことがあります。 私も「どうして靴下を?」って言われたら、正直なところ、父から継承しながらやってきたというところなんですが。同じように作ろうとしても職人が違うと同じものができないだとか、同じ機械を使っても職人によっては違うものができるだとか、そういうのも楽しみで、深掘りしていくともっと面白いことができるんじゃないかなっていうのはありまして。そういうのが、長年続けている理由かもしれません。 僕らは、健康は足元からって言っていて。足をサポートするっていうのは当然靴ですけど、そのなかに靴下っていうのがあって、みなさんが健康に明るく生活できるためのひとつのものだと思っています。もっともっと良いものを開発して、もっとみなさんに愛されるようなものを作れないかな?という想いがあるから継続してるような感じだと思ってます。 神野:本当に色んな靴下があって、それこそ100円で買えるような靴下も出てきてるじゃないですか。さっき健康は足元からっていう話がありましたけど、僕は高校生のときは靴下へのこだわりは持ってなかったんですけど、色々経験したなかで、靴下はパフォーマンス向上にも繋がるし、みなさんにもっと重要視してほしい部分だなって感じてるところです。この対談を見てくださってる方には、「RETO × IDATEN」が一味違う靴下だというのを感じてもらいたいなって思います! そういえば、さっきUNIVALさんのほかの商品をいただいて、さっそく今履いてるんですけど、これもすごく履きやすいですね。 横山:ありがとうございます。今神野さんに履いてもらってる「寒がり靴下職人が作ったソックス」というのはうちの商品で一番あったかい靴下なんですよ。 冬は暖かい、夏は涼しい、運動のときは汗を吸って、という風に、靴下を履くにも色んなシーンがありますよね。季節もそうですし、履くシーンを色々想定したなかで、それに一番適したものは何なのかを考えてまして。「RETO × IDATEN」に関してはランニングに適してる、「寒がり靴下職人が作ったソックス」に関しては寒さに適してる、シーンごとの一番の履き心地にこだわっています。 神野:それぞれのニーズに合ったものをっていうことですね。 横山:そうですね!ニーズに合ったものを一番良い価格でご提供できればと、そういう想いで作っています。 靴下=人海戦術 自慢の靴下には職人技が詰まっている 横山:最後に、私のほうから神野さんに1つ質問させてください。 今日、兵庫県加古川市のほうにわざわざ来てもらって。1年前から神野さんとやりとりさせてもらって、コロナ禍でなかなか会えなくてリモートばかりで、サンプルを送り込んでフィードバックをもらってっていうやりとりをずーっとやってきたなかで、今日こうやってわざわざお越しいただいて、うちの工場でどうやって靴下ができるのかっていうのを見ていただけたのがメーカー側としてはすごく嬉しいです。 商品ができあがったタイミングというのもあられると思うんですが、なぜ来ていただけたのかな?と、興味津々です。 神野:はい、これまでずっと競技で陸上をやってきて色んな靴下を履いてきたんですけど、どうやって靴下が作られてるかってところに興味を持ったことがなかったんですよ。でも、今回自分のブランドの「RETO」っていうところで商品を発売させていただくっていうことで、靴下がどうやって作られてるのかっていうところに単純に興味を持ちまして、見せていただけるのであれば見たいなと思いました。 やっぱり実際に見せてもらうと想像を超えてるというか。機械も自分では絶対に扱えなさそうな、見たことないようなもので。やっぱり自分で見るっていうのは大事な時間だったなという風に思いました。 あの機械、本当にすごいですよね……。 横山:うちの工場には技術者が今4人いて、みんな15年から20年、長い人は30年くらいのベテランの方たちばかりです。...
職人の感性が「一番の履き心地」を生み出している ──神野大地×靴下老舗メーカー社長対談(後編)
Text: yuki yoshida 2022年4月、神野大地が手がけるブランド「RETO(レト)」からランニングソックスが販売スタート。同商品は、日本三大靴下産地である兵庫県加古川市に自社工場を構えるUNIVAL(株式会社ユニバル)と共同開発し、約1年かけて完成した。 2月には実際に兵庫県加古川市にある工場を見学。本記事では、工場見学後にUNIVALの横山社長と神野が行った対談を公開する。 後編では、普段あまり知る機会がない靴下製造の“中の話”に触れていく。横山社長のこだわりやものづくりにかける想いを垣間見ることができるだろう。 ランニングには、ランニングに一番適した靴下を 神野:お話を聞いていると、靴下ってとても繊細ですよね。作るのにも時間がかかっていたり、そんなに高い商品ではなかったりがあると思うんですけど、どうして靴下にこだわり続けているのかっていうのは何か理由がありますか? 横山:そうですねー。うちの会社は製造も踏まえますと56年目に入っていて、創始者がうちの父で、私が二代目っていう形でやらせていただいてます。 兵庫県の加古川市の地場産業として靴下の製造があります。これは私もうちの父から聞いたんですけど、加古川市の志方町っていうところは昔綿花を栽培してたところで、そういう繋がりで靴下っていうのがこの地に生まれました。もっと古くからいうと、ある方が中国から編み機を1台持って帰ってきて、ここで育った綿花を紡いで靴下を作ったっていうのが最初だと聞いたことがあります。 私も「どうして靴下を?」って言われたら、正直なところ、父から継承しながらやってきたというところなんですが。同じように作ろうとしても職人が違うと同じものができないだとか、同じ機械を使っても職人によっては違うものができるだとか、そういうのも楽しみで、深掘りしていくともっと面白いことができるんじゃないかなっていうのはありまして。そういうのが、長年続けている理由かもしれません。 僕らは、健康は足元からって言っていて。足をサポートするっていうのは当然靴ですけど、そのなかに靴下っていうのがあって、みなさんが健康に明るく生活できるためのひとつのものだと思っています。もっともっと良いものを開発して、もっとみなさんに愛されるようなものを作れないかな?という想いがあるから継続してるような感じだと思ってます。 神野:本当に色んな靴下があって、それこそ100円で買えるような靴下も出てきてるじゃないですか。さっき健康は足元からっていう話がありましたけど、僕は高校生のときは靴下へのこだわりは持ってなかったんですけど、色々経験したなかで、靴下はパフォーマンス向上にも繋がるし、みなさんにもっと重要視してほしい部分だなって感じてるところです。この対談を見てくださってる方には、「RETO × IDATEN」が一味違う靴下だというのを感じてもらいたいなって思います! そういえば、さっきUNIVALさんのほかの商品をいただいて、さっそく今履いてるんですけど、これもすごく履きやすいですね。 横山:ありがとうございます。今神野さんに履いてもらってる「寒がり靴下職人が作ったソックス」というのはうちの商品で一番あったかい靴下なんですよ。 冬は暖かい、夏は涼しい、運動のときは汗を吸って、という風に、靴下を履くにも色んなシーンがありますよね。季節もそうですし、履くシーンを色々想定したなかで、それに一番適したものは何なのかを考えてまして。「RETO × IDATEN」に関してはランニングに適してる、「寒がり靴下職人が作ったソックス」に関しては寒さに適してる、シーンごとの一番の履き心地にこだわっています。 神野:それぞれのニーズに合ったものをっていうことですね。 横山:そうですね!ニーズに合ったものを一番良い価格でご提供できればと、そういう想いで作っています。 靴下=人海戦術 自慢の靴下には職人技が詰まっている 横山:最後に、私のほうから神野さんに1つ質問させてください。 今日、兵庫県加古川市のほうにわざわざ来てもらって。1年前から神野さんとやりとりさせてもらって、コロナ禍でなかなか会えなくてリモートばかりで、サンプルを送り込んでフィードバックをもらってっていうやりとりをずーっとやってきたなかで、今日こうやってわざわざお越しいただいて、うちの工場でどうやって靴下ができるのかっていうのを見ていただけたのがメーカー側としてはすごく嬉しいです。 商品ができあがったタイミングというのもあられると思うんですが、なぜ来ていただけたのかな?と、興味津々です。 神野:はい、これまでずっと競技で陸上をやってきて色んな靴下を履いてきたんですけど、どうやって靴下が作られてるかってところに興味を持ったことがなかったんですよ。でも、今回自分のブランドの「RETO」っていうところで商品を発売させていただくっていうことで、靴下がどうやって作られてるのかっていうところに単純に興味を持ちまして、見せていただけるのであれば見たいなと思いました。 やっぱり実際に見せてもらうと想像を超えてるというか。機械も自分では絶対に扱えなさそうな、見たことないようなもので。やっぱり自分で見るっていうのは大事な時間だったなという風に思いました。 あの機械、本当にすごいですよね……。 横山:うちの工場には技術者が今4人いて、みんな15年から20年、長い人は30年くらいのベテランの方たちばかりです。...
